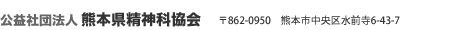協会誌巻頭言
当協会について新年のごあいさつ
― 熊精協の会長を拝命して ―
くまもと心療病院 荒木 邦生
明けましておめでとうございます。新しい年を迎えるにあたり,皆様にご挨拶をさせていただきます。
2025年5月の総会において前会長の相澤明憲先生の退任にともない,熊精協の会長を拝命しました。私は年齢が相澤先生の2歳下という同年代であり,相澤先生が12年にわたり会長を務められたため,今回は会長も含め役員は若返るべきと考えていました。しかし日本においても熊本においても,精神科医療に大きな変化が想定される時期に,熊精協においては会員病院とともに,まとまって落ち着いた対応が必要かもしれないと考えて,70歳も近い年齢ではありますが,繋ぎ手としての役割を果たす意味で引き受けました。
まず日本の精神科医療の変化についてです。2024年度は我々民間の精神科病院の7割が赤字経営でした。診療報酬が低く抑えられている上に,物価高騰や人手不足,人口減少とコロナ禍後の受診控え等による病床利用率低下などが原因と言われています。また国は精神科病床を5万3千床減らすことを検討しています。赤字経営については,来年の改定で診療報酬が上がらないと多くの病院が瀕死の状態になると思いますが,報酬アップは病床削減とセットになると思われます。地域医療構想に精神科が入ることが決まり,来年度から病床機能報告が始まり,地域における病床適正化の具体的数字が出てくると考えられます。古くなった病院を新しく建て替えようと思っても,建築コストの著しい上昇により簡単にはできません。そのような状況で病院の事業継承問題などがあれば,病院経営を継続するかどうかを悩む病院も出てきて,今後は病床数だけでなく病院数も減るかも知れません。何十年と続いてきた精神科医療が変わらざるを得なくなっています。このような大きな変化に対応するには,若い経営者の力が必要になります。私は若くはありませんが,新しく熊精協の理事になられた若い先生方とともに,このような問題に取り組んで参りたいと思っています。
熊本においては熊本大学精神科医局の問題がありました。これは多くの先生方が大変心配されていた問題です。熊大の精神科医局から医局員がほとんど居なくなるという事態になりました。これについては様々の先生方が様々な考えや思いを持っておられると思います。またすでに新しい教授である牧之段学先生が,2025年10月1日から熊大精神科教授として赴任されておられます。今後は牧之段教授を中心に新たな熊大精神科医局が運営されることとなり,この問題はまずは一件落着となりました。この問題の解決に尽力された方々に心から感謝しております。この問題について,私がいまさら触れる必要はないのかもしれませんが,今後のことを考えて私なりの意見を言わせていただきます。
私は今のシステムがどう影響しているのか,若い先生方のマインドがどう変化しているのかという視点で考えてみました。
私の年代は精神科医になろうと考えたら,大学の精神科医局に所属して研修医として2年間勉強し,その後は医局の人事で動くことが当たり前でした。しかしご存知のように,研修医マッチングシステムが始まり,プログラムを実施できる病院であれば,研修医を受け入れることができるようになりました。大学卒業時に希望した病院とコンピューターでマッチングすれば,どこででも正式な臨床研修を受けることができます。精神科医になるために大学の精神科医局に所属する必要がなくなったのです。昨今は熊本だけでなく全国の大学の医局の弱体化が叫ばれています。その原因の一つがシステムの変更だと思います。私個人としては,若い医師をしっかり教育することや,医師の都市部偏在を改善し地域医療を守るために,ある程度は大学の医局にマンパワーと人事権があったほうが良いと思っています。しかし今はこのシステムの中で,どのようにして医師を確保するかを考えなければなりません。
また若い世代の人たちにある程度共通しているのは,組織の中で嫌な思いをしてまで我慢しなくなっていることです。私の時代は選択肢が無い上に,義理とか忠誠心という古典的思考を持っている人が多くいました。しかし今の若い世代の人たちは自由であり,多くの選択肢から自分に合うと思うものを選べばよいし,それがごく普通なのです。
最近「直美(ちょくび)」という言葉をよく耳にします。それは2年間の初期研修システムを終了した後に,直ぐに美容整形クリニックに就職する若い医師が多いことを意味しています。皆がそうではありませんが,自由な時間があって,稼げる仕事が良いと思う人が多いのです。「安易である」などと批判しても仕方ありません。そのような状況の中で,仮に組織が権威主義的で自由の無いものだったなら,誰もそこを選びません。よって若い医師たちに「自分の将来のために是非この教室で学びたい」「ここで研究をして多くの人の役にたちたい」と思ってもらい,選んでもらう必要があります。そしてその場所が,明るく自由で活気に満ちたところであるなら,人が居なくなることなどないと思います。そのようにマネジメントすることは簡単ではないと思いますが,牧之段教授には心から期待をしています。
また熊大精神科医局と熊精協の会員病院や診療所が対立するような状況では,熊本の精神科の未来は明るくなりません。私たち熊本県精神科協会は,牧之段教授と新しい熊本大学精神科医局に協力し,しっかりとタッグを組んで2026年を,再び熊本で多くの若い精神科医師が育ってゆく環境を整えるための,新たな年にしたいと考えております。
協会誌巻頭言のダウンロード
協会誌巻頭言をPDF形式で閲覧・ダウンロードできます。
- 協会誌巻頭言「新年のごあいさつ」(PDF)
- 協会誌巻頭言「不亦楽乎」(PDF)
- 協会誌巻頭言「しんそしんみつ」(PDF)
- 協会誌巻頭言「公立・公的病院の役割~インクルーシブな社会を目指して~」(PDF)
- 協会誌巻頭言「新年のご挨拶」(PDF)
- 協会誌巻頭言「私の愛おしい小さな子供達」(PDF)
- 協会誌巻頭言「テクノロジーとの共存」(PDF)
- 協会誌巻頭言「新年のご挨拶」(PDF)
- 協会誌巻頭言「精神科医療と身体、連携について」(PDF)
- 協会誌巻頭言「電気代高騰と脱炭素」(PDF)
- 協会誌巻頭言「熊本地震8年を迎えて」(PDF)
- 協会誌巻頭言「新年のご挨拶」(PDF)
- 協会誌巻頭言「今までの人生を振り返り,更に今後の生き方について」(PDF)
- 協会誌巻頭言「もうひとつのパンデミック」(PDF)
- 協会誌巻頭言「新型コロナの行方」(PDF)
- 協会誌巻頭言「新年のご挨拶」(PDF)
- 協会誌巻頭言「人権制限の必要性と有害性」(PDF)
- 協会誌巻頭言「コロナ禍における覚悟」(PDF)
- 協会誌巻頭言「熊精協との30年」(PDF)
- 協会誌巻頭言「新年のご挨拶」(PDF)